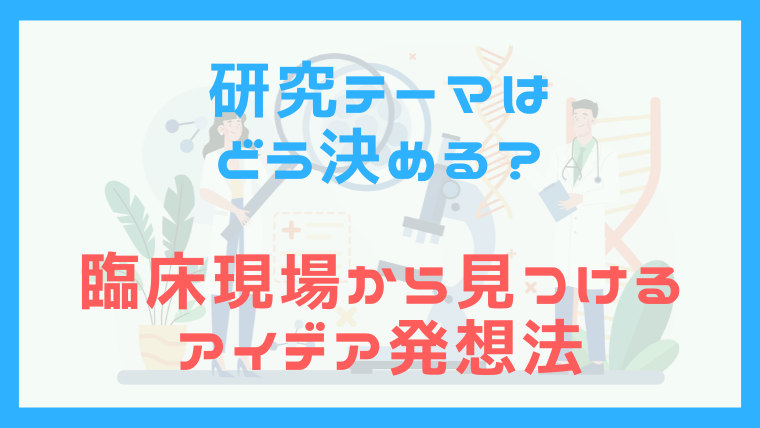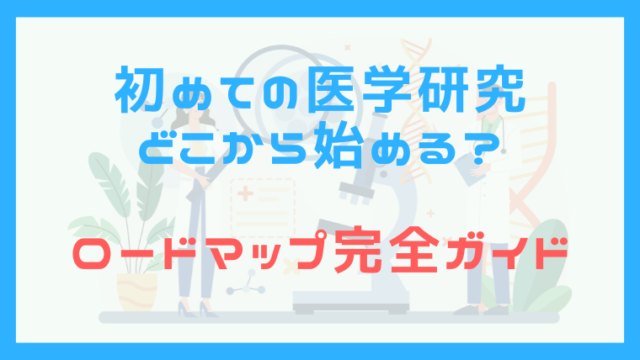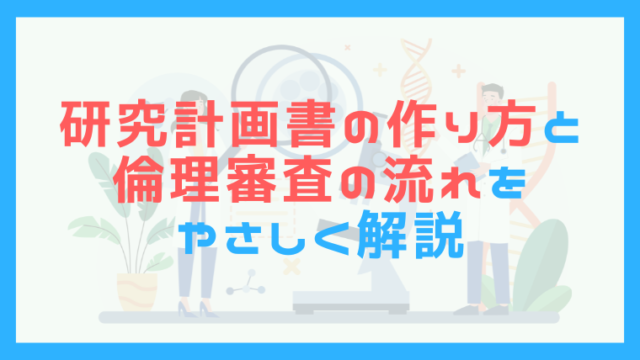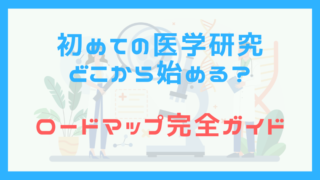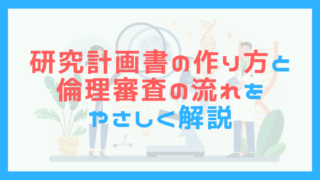はじめに — テーマが決まらないと研究は始まらない
「研究をやってみたいけれど、テーマが全然思い浮かばない」
「先行研究を見てもピンとこない…」
これは研究初心者によくある悩みです。
研究テーマは研究全体の方向性を決める「設計図」のようなもの。
ここがあいまいだと、後の計画・解析・論文化も迷走してしまいます。
私も最初は「何をテーマにするか」で長く悩みました。
現在は医学博士・理学療法士として疫学・公衆衛生分野の研究を行いながら、ココナラで研究初心者〜中級者のサポートもしていますが、その経験から言えるのは…
テーマ選びは「才能」ではなく「やり方」で決まる ということです。
この記事では、臨床現場からテーマを見つける具体的な発想法と、選び方のコツをやさしく解説します。
よくある「ダメなテーマ」の選び方
テーマ決めでつまずく最大の理由は、「なんとなく」で選んでしまうことです。
たとえば、次のような選び方には注意が必要です。
- 興味はあるがデータが存在しない
- 調べたい対象が少なすぎる(nが確保できない)
- 倫理審査を通らないリスクがある
- 実施に時間やコストがかかりすぎる
- 臨床的な意義が乏しい
こうしたテーマは、途中で行き詰まったり論文化できなかったりするリスクが高いです。
「関心 × 実現可能性 × 臨床的意義」で考える
良いテーマは、この3つが揃っています。
| 軸 | 内容 | チェックポイント |
|---|---|---|
| 関心 | 自分が興味を 持てること |
日常業務で気になっていること 学会や論文で目にするたびワクワクする話題 |
| 実現可能性 | 実際に研究 できるか |
データが入手できる 症例数が十分ある 倫理審査を通る内容である |
| 臨床的意義 | 臨床や現場に 役立つか |
患者や現場に還元できる 既存研究の不足を補える |
最初は、関心を出発点にして構いません。
そこから「実現可能性」「臨床的意義」の観点でふるいにかけると、実行可能なテーマが絞れます。
アイデアを見つける3つの具体的な方法
テーマは突然ひらめくより、「探す」ものです。
初心者でも取り組みやすい3つの探し方を紹介します。
📝 ① 日常業務や記録から拾う
- カルテ記載、業務日報、カンファレンス議事録などを見返す
- 「いつも疑問に感じていること」「モヤモヤする課題」をメモする
- 患者や利用者の声からヒントを得る
例:「○○の患者さんは回復が遅い気がする」「在宅復帰率に差があるのはなぜ?」など
📚 ② 先行研究をざっと検索する
- PubMedやGoogle scholarで検索
- 気になるキーワードでまずはタイトルと要旨だけ読む
- 「既にたくさんある研究」と「まだ少ない研究」を見極める
研究の「穴」を探す意識が重要です
💬 ③ 周囲と話してみる
- 指導教員や上司、同僚に雑談感覚で相談する
- 「このデータがあるけど何かに使えないかな?」と共有する
- チームでブレストしてみる
自分では当たり前と思っている視点が、他人から見ると価値あるテーマになることもあります
成功しやすいテーマ決定の進め方(ケース紹介)
以下は、私がサポートした研究初心者の事例をもとに構成を変えたフィクションです。
🦵 ケース:理学療法士が初めて研究テーマを決めた例
- 背景:理学療法士5年目、日々の臨床業務が多忙で研究経験はなし
- 手持ちデータ:退院患者の歩行能力評価(n=100)
- 進め方
1. リハビリ記録を振り返り、「在宅復帰者は入院初期の歩行速度が高い気がする」と気づく
2. PubMedで検索 → 同様の先行研究はあるが日本人対象は少ないと判明
3. 同僚とディスカッション → 実現可能と判断し研究計画書を作成
4. 倫理審査に申請 → 承認
5. データ解析と図表作成 → 抄録執筆 → 学会発表 - 結果:初めての研究として成功体験となり、その後論文化も視野に
このように、日常臨床から気づきを拾い、関心×実現可能性×臨床的意義の3軸で検討することで、理学療法分野でも研究テーマを決めることができます。
よくある質問(Q&A)
Q. 興味があるテーマがいくつもあって選べません…
→ まずは関心・実現可能性・臨床的意義の3軸で点数をつけてみましょう。最もバランスが良いものを優先します。
Q. 既に似た研究があるとやる意味がない?
→ いいえ。同じテーマでも対象・方法・時期が違えば価値があります。
むしろ先行研究がある方が、審査や論文化もしやすいです。
Q. データがなくても始められますか?
→ 可能です。まずは「調査計画」だけを立て、データ収集を今後行う前提で進める方法もあります。
📚 参考文献
※以下のリンクはアフィリエイト(広告)を含みます。
まとめ
- テーマは「関心 × 実現可能性 × 臨床的意義」で絞る
- アイデアは「日常業務」「先行研究」「周囲との会話」から探す
- 先に完璧を目指さず、まずは「決めて進める」ことが大切