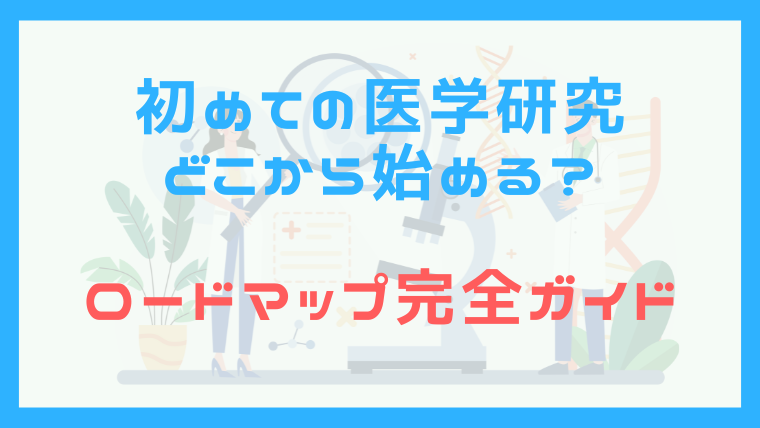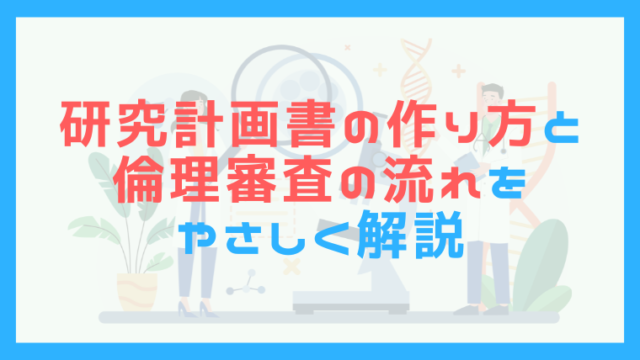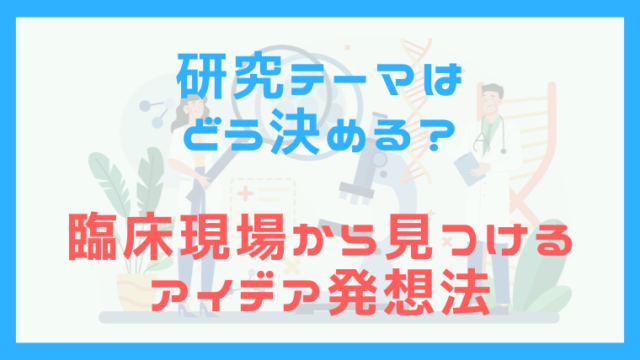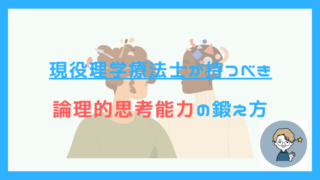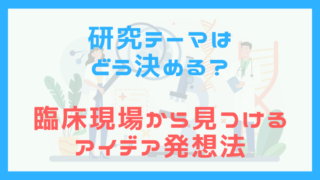はじめに — 研究を始めたいけど、何から手をつければいい?
「研究に興味はあるけど、何から手をつければいいのかわからない」
「論文を書いてみたいけど、臨床業務が忙しくて時間が取れない…」
こうした悩みを抱える医療職は非常に多くいます。
医療現場では日々の臨床が最優先されるため、体系的に研究を学ぶ機会が少なく、「やりたい気持ちはあるのに一歩を踏み出せない」状態になりがちです。
私自身も、かつては臨床業務と研究の両立に悩んできました。
その経験を活かし、現在は医学博士・理学療法士として疫学・公衆衛生分野の研究を行いながら、ココナラで研究初心者〜中級者への支援も行っています。
この記事では、初めて研究に挑戦する方に向けて、研究の全体像(ロードマップ)をわかりやすく解説します。
研究は6つのステップで進める
医療研究を効率的に進めるには、最初に全体像を把握することが何より重要です。
研究は次の 6ステップ で進めるのが王道です。
医療研究の基本的な流れ
- テーマ設定
- 研究計画(デザイン作成・倫理審査申請)
- データ収集
- データ解析
- 論文執筆
- 学会発表・論文投稿
どのステップも欠かせませんが、最初に全体像をつかんでおくことで、途中で迷子にならずに進められます。
なぜ全体像を知ることが大切なのか
「とにかくやってみる」精神は素晴らしいですが、研究では設計を飛ばして始めると失敗する確率が非常に高くなります。
よくある失敗例を挙げると…
- 倫理審査を通していなかった
- データを集めた後に「倫理審査が必要だった」と判明 → データを使えない
- サンプルサイズ不足
- nが少なすぎて有意差が出ず、論文化できない
- 統計計画を立てずに解析
- 後から「不適切な解析」と判断され、査読でリジェクト
どれも「最初に設計をせずに見切り発車した」ことが原因です。
研究は「ゴール(論文化)」から逆算して設計することがとても大切です。
初めての研究が形になった実例
ここでは、私がサポートした研究に初めてチャレンジした方の事例を紹介します(個人情報は匿名化し、一部内容はフィクションです)。
ケース:看護師が初めて挑戦した臨床研究
- 背景:看護師3年目、患者満足度調査のデータ(n=120)を保有
- 当初の悩み:「とりあえずデータはあるけど、何をどうすればいいか分からない」
- 進め方
1. テーマを絞る
– 「満足度と看護師対応時間の関連」に注目
2. 仮説を立てる
– 「対応時間が長いほど満足度が高い」という仮説を設定
3. 倫理審査を申請
– 書類作成とチェックをサポート
4. 統計ソフトで解析
– 記述統計 → 群間比較 → 重回帰分析
5. 結果を図表化し、論文構成案を作成
6. 学会発表準備(抄録・スライド添削) - 成果:無事に学会発表を終え、その後英語論文化にも成功
このように、全体像と順序を理解していれば、研究初心者でも確実に形にできます。
最初に意識すべき3つの視点
初めて研究に挑戦する際に、いきなり統計や論文ルールを完璧に覚える必要はありません。
それよりも、まずは次の3つを意識してください。
① 全体の流れをつかむ
- 研究には「テーマ→計画→収集→解析→執筆→発表」という明確な流れがある
- 最初に流れを理解しておくと、無駄な手戻りを防げる
② 目的と仮説を明確にする
- 「何を明らかにしたいのか」を明確にしないと、途中で迷走しやすい
- 仮説があれば、必要なデータや解析方法も自ずと見えてくる
③ 必要に応じて専門家に相談する
- 研究初心者が1人ですべてを行うのは非現実的
- 限られた時間の中では「学ぶ」より「支援を受ける」方が効率的な場面も多い
よくある質問(Q&A)
Q. 研究テーマが思いつきません…
→ 最初は「日常業務で気になっていること」を書き出してみましょう。
関心×実現可能性×臨床的意義の3軸で絞ると決めやすくなります。
Q. 統計が苦手でもできますか?
→ 大丈夫です。
最初は記述統計や群間比較などシンプルな解析でも十分研究になります。
必要に応じて外注などの支援を受けてもOKです。
Q. 忙しくて時間が取れません…
→ 最初から論文化を目指す必要はありません。
学会抄録→ポスター発表→論文化、と小さなステップで進めると続けやすいです。
📚 参考文献・引用
※本ブロックの一部リンクには広告(アフィリエイト)を含みます。
まとめ
- 医療研究は「テーマ→計画→収集→解析→執筆→発表」の6ステップで進める
- 全体像を知らないと、時間も労力もムダになりやすい
- 最初は「流れ・仮説・相談」の3つを意識して進めよう
次の一歩
臨床業務をこなしながら研究を進めるのは簡単ではありません。
「研究計画づくりでつまずいている」「何から始めるべきか整理したい」と感じているなら、個別相談を通じて効率的な進め方を一緒に考えるという選択肢もあります。