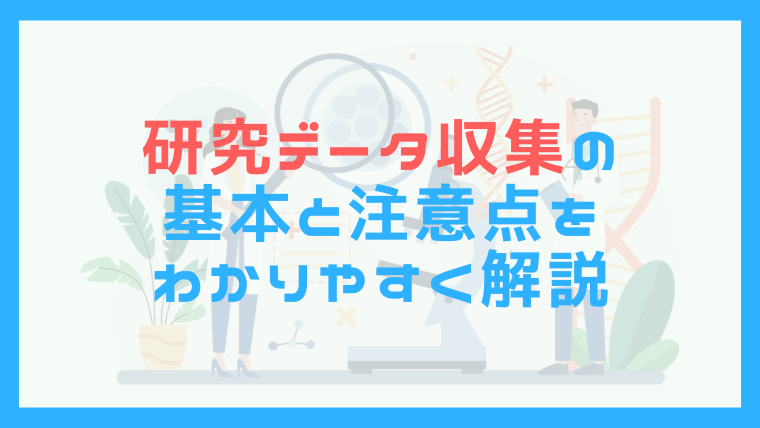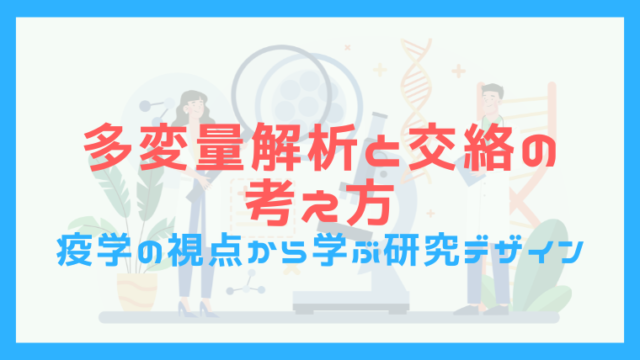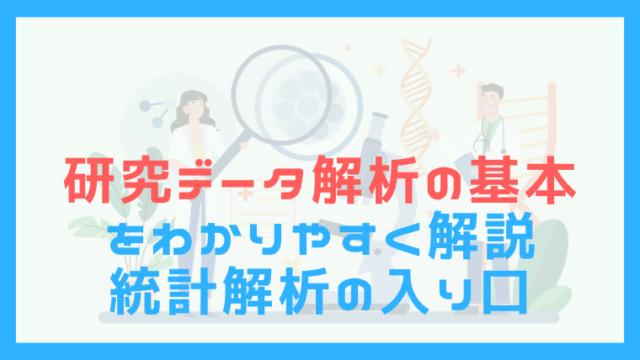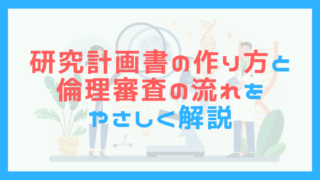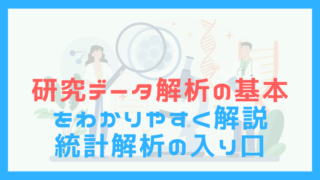「研究計画書は作ったけれど、実際のデータ収集はどうすればいいの?」
「データを集めるときに、漏れやバイアスが出ないか心配…」
研究初心者の多くがつまずくのが、この データ収集 です。
計画があっても、正しくデータを集めなければ信頼できる結果にはつながりません。
そこで本記事では、研究データ収集の基本と注意点 を、わかりやすく整理しました。
研究データ収集の基本ステップ
① データ収集方法を決める
あなたの研究が 観察研究なのか、介入研究なのか によって収集方法は変わります。
- 観察研究 → 診療録、アンケート、既存データベース
- 介入研究 → 介入前後の測定、追跡調査
重要なのは、計画書に書いた方法と一致させること。審査で承認された手順を勝手に変更すると、研究の信頼性が損なわれます。
② データの標準化を意識する
同じ変数を測定しても、人によってやり方が違うとデータがばらつきます。
例えば「血圧測定」で、腕の高さや測定時刻が違うと結果は揺らぎます。
標準作業手順書(SOP) を作っておくと、研究メンバー全員が同じ基準で測定できます。
③ データ入力・管理の仕組みを作る
収集したデータは、そのままでは使えません。
ExcelやSPSS、Stataなどに入力する際は、入力ルールをあらかじめ決めること が重要です。
- 欠損値は「999」と入れるか「空欄」とするか
- 連続値は小数点1桁までか2桁までか
こうしたルールがないと、解析時にトラブルになります。
データ収集で注意すべきポイント
① バイアスを最小限にする
データ収集で最も注意すべきは バイアス(偏り)。
- 記録の抜け漏れ
- 調査対象が特定の集団に偏っている
- 測定者による差
これらは研究結果の信頼性を大きく損ねます。
可能であれば ダブルチェック体制 を作りましょう。
② 倫理的な配慮を徹底する
データ収集の段階でも、倫理的配慮は欠かせません。
- インフォームドコンセントに沿った収集になっているか
- 個人情報を適切に匿名化できているか
「集めること」だけに意識が集中すると、研究倫理を忘れがちです。常に対象者への配慮を優先してください。
③ データの保存とセキュリティ
紙媒体・電子媒体どちらでも、データ管理の基本は 紛失と漏洩を防ぐこと。
- 紙:鍵付きキャビネット
- 電子:パスワード付きPC、暗号化クラウド
研究データは極めて重要な資産。保管ルールを定め、定期的に見直しましょう。
よくある質問(Q&A)
Q. データはどれくらいの期間保存すべき?
多くの施設では 5年間保存 が一般的。ただし学会・ジャーナルの規定に従うこと。
Q. データ入力は外注してもいい?
はい。ただし 個人情報を含まない形で委託する ことが必須。ココナラでは守秘義務契約(NDA)を締結している人であれば安心です。
もちろん、私もNDAを締結していますので、安心してご依頼可能です!
出品サービス以外でも「こんな事はやってくれるか?」など、お気軽にご相談ください。
→ あうとろ@医療系コンサル [リンク]
Q. 紙と電子、どちらで管理すべき?
併用がベスト。紙は原本保存、電子は解析用としてコピーを作成すると効率的です。
まとめ
- 研究データ収集は「計画と標準化」がカギ
- バイアスを防ぐためにチェック体制を構築
- 倫理配慮とセキュリティ対策は必須
- 入力ルールを統一して、後の解析をスムーズに
研究の成果は、データの質に大きく左右されます。
あなたの研究も、「正しくデータを集めること」 から始まるのです。
参考文献
※リンクの一部はアフィリエイト広告を含みます。