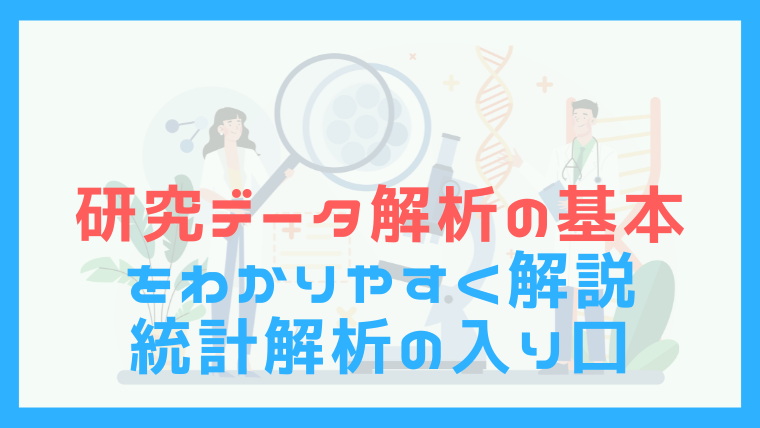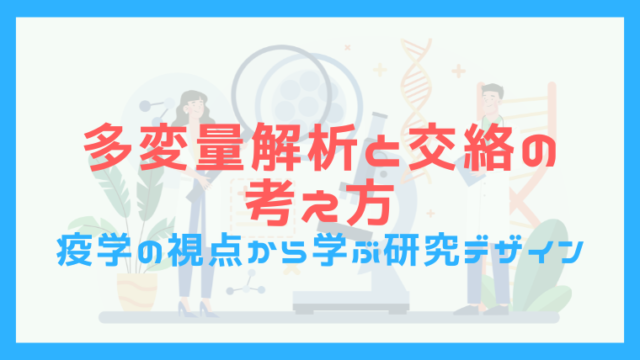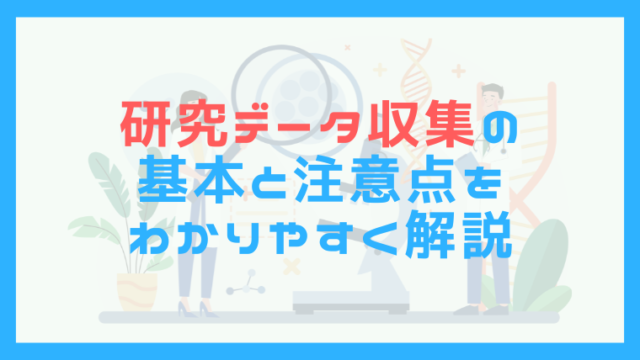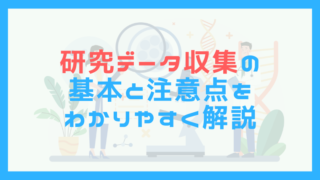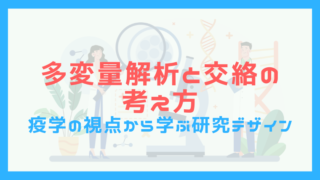「データは集めたけれど、どう解析すればいいのか分からない」
「統計の勉強をしたことはあるけど、研究でどう使えばよいか迷う」
臨床や研究の現場でよく聞く悩みです。
データ解析は研究の要。正しい方法で行わなければ、せっかく集めたデータも意味を持たなくなります。
本記事では、研究初心者に向けて統計解析の入り口となる基本ステップを解説します。
研究データ解析の基本ステップ
① データの確認
まずはデータの中身を把握することから始めます。
– サンプルサイズ(n)は十分か?
– 欠損値はどのくらいあるか?
– 平均値や中央値などの記述統計
ここを飛ばすと、解析の方向性を誤ることがあります。
② 記述統計で全体像をつかむ
研究の最初の解析は記述統計です。
– 平均・標準偏差
– 中央値・四分位範囲
– クロス集計(例:男女別の割合)
これだけでも「対象者の特徴」が明確になり、論文のTable 1としてよく使われます。
③ 仮説検証のための統計解析
次に仮説検証の段階です。
– 2群比較:t検定、Mann-Whitney U検定
– 多群比較:ANOVA、Kruskal-Wallis検定
– 変数間の関連:相関係数、χ²検定
あなたの研究目的に合わせて手法を選びましょう。
研究でよく使われる解析手法の入口
① 回帰分析
変数間の関係を調べる基本的な方法です。
– 単回帰分析:ある1つの要因と結果の関係
– 多変量回帰分析:複数の要因を同時に考慮
例:「年齢・性別・BMIが血圧に与える影響を検討」
② 生存時間解析
「イベントが起きるまでの時間」を解析する方法。
臨床研究で死亡・再発・転倒などを扱うときに必須です。
– Kaplan-Meier法
– Cox比例ハザードモデル
③ 多変量解析の考え方
現実のデータは要因が複雑に絡み合います。
多変量解析は「交絡因子」を調整して、より純粋な関連を明らかにする手法です。
データ解析で注意すべきポイント
① データの質が結果を左右する
どれだけ高度な統計手法を使っても、元データが不十分なら意味がありません。
データ収集の質を担保することが大前提です。
② 適切な統計手法を選ぶ
手法を誤ると、誤った結論にたどり着きます。
「連続変数なのにχ²検定を使ってしまう」などは初心者にありがちなミスです。
③ 再現性を意識する
統計解析は誰がやっても同じ結果になることが重要です。
解析の流れを記録したり、スクリプト(RやStataのコード)を保存しておくと再現性が高まります。
まとめ
– 研究データ解析は確認 → 記述統計 → 仮説検証の流れが基本
– 回帰分析や生存時間解析は臨床研究でよく用いられる
– データの質・手法の適切さ・再現性が研究の信頼性を左右する
研究解析の基本を押さえて、次のステップへ進みましょう。
参考文献
- 新谷歩:今日から使える医療統計 第2版.医学書院 [リンク]
- 山田実:メディカルスタッフのためのひと目で選ぶ統計手法〜「目的」と「データの種類」で簡単検索! 適した手法が76の事例から見つかる、結果がまとめられる.羊土社 [リンク]
- 道端伸明ら:医療統計、データ解析しながらいつの間にか基本が身につく本〜Stataを使ってやさしく解説.羊土社 [リンク]※一部アフィリエイト広告が含まれています。